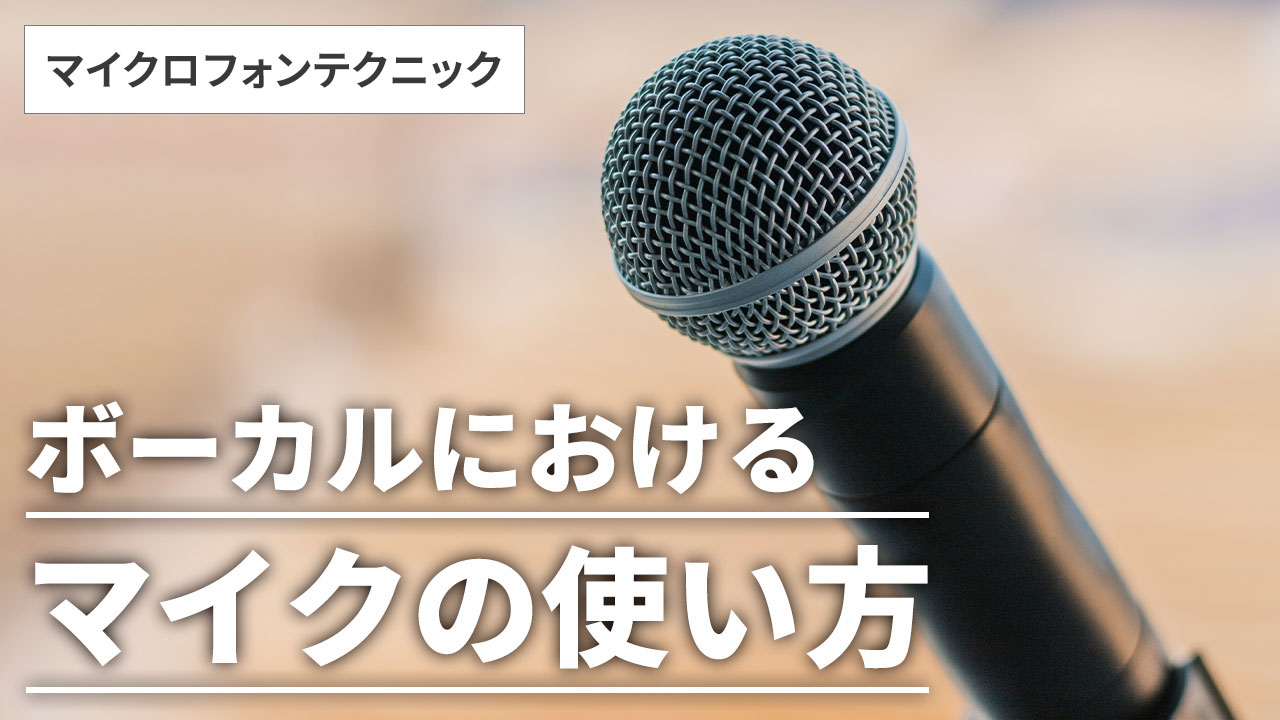ボーカリストの歌声を収音するマイクは様々な場面で使用されており、使い方もシンプルで扱いやすい音響機器だと思われがちです。
しかしマイクは、距離、角度などのポジションで音が大きく変化し、扱い方を間違えると素晴らしい歌声も台無しになってしまう難しい機器です。本記事ではライブ、カラオケ、レコーディングなどのシチュエーションに合わせた正しいマイクの使い方を解説します。
ライブ・カラオケにおけるマイクの使い方

ライブやカラオケでは手で持つタイプのハンドヘルド型マイクを主に使用します。
マイクを持つ際はグリル下部のグリップ部分を持つようにしましょう。

下図のようにグリル部分を手で覆ってしまうと、共鳴によって音質が変化してしまい、スピーカーから「キーン」という音が鳴る「ハウリング」という現象の原因にもなるので気を付けましょう。

また、マイクをスピーカーに向けることもハウリングの原因となるので、マイクを向ける方向にも気を配りましょう。
そして、ハンドマイクはグリル先端部分が収音の中心となるため、先端部分を口元から数cm離れるくらいに近づけます。グリル横ではマイク本来の収音性能を発揮できないので、注意しましょう。

この距離だと、低音域が強調された力強い音質になります。ミキサーなどの外部機器に装備されているイコライザーで低域をカットすることにより自然な音質に調整できます。
また、マイクとの距離、角度を調整することで、歌い手自身で音質を変化させることも可能です。口元から数cmの距離を基準としながら、歌の表現に合わせてマイク位置を調整することで、より多彩な表現が可能です。
マイマイクを導入しよう
ライブハウスやカラオケボックスには備え付けのマイクが用意されていますが、昨今はマイマイクを購入する方が増えています。
マイマイクを購入することで、音質やマイクの握り心地など、自分の好みに合ったマイクを使用することができます。また、複数人でマイクを使い回す必要がなくなるため、感染症対策など衛生面においても安心です。
ハンドマイクは安いものは数千円程度、プロが使うレベルの製品でも1~2万円程度で購入できます。別の記事でハンドマイクの選び方を解説していますので、参考にしてください。

ダイヤフラムの厚みを中心部と外縁部で変えることでダイヤフラムの動きを適切に制御する、独自のバリモーション・テクノロジーを採用。
レコーディングにおけるマイクの使い方

自宅やスタジオでのボーカルレコーディングでは、より繊細に音を拾えるサイドアドレス型のコンデンサーマイクを用いることが多いです。

C414 XLIIの音質を受け継ぎながらも、機能を限定することで優れたコストパフォーマンスを実現。ライブシーンにも積極的に活用可能。
サイドアドレス型マイクは、収音する振動板(ダイヤフラム)が筐体内に垂直に配置されているため、グリル正面部分が口元にくるよう、マイクを地面に対して垂直に設置します。

正面の音を中心に拾う単一指向性のマイクでは歌い手の唇と鼻の間にマイク収音部分を向けて、口元から20~30cmほど距離を取ります。
収音時に吹き付けた息や、パ行、バ行、タ行、ダ行などの破裂音が目立つ場合は歌い手の唇を少しだけマイクから離すか、ポップノイズを抑制するアクセサリーであるポップフィルターを使用しましょう。

レコーディングにおいても、マイクとの距離や角度を調整することで、歌い手自身が音質を調整することが可能です。マイクとの距離は20~30cmを基準とし、状況に合わせて調整することで多彩な表現が可能です。
また、ボーカルレコーディングではクリアに声を収音するために部屋の音響を意識することも重要です。歌い手の周りを障壁などで取り囲み、反射音を減らすことでクリアな聴きやすい音を収音することができます。
比較的手軽に導入できるリフレクションフィルターや音響拡散体などは、部屋の反射音を整えるのに有効なアイテムです。

「オトノハ」は葉の成長をモチーフに、新たな発想から生まれた”音響拡散体”です。オーディオ再生やレコーディング、楽器演奏など音にこだわりたい空間に。

なお、すべての方向から収音する無指向性のマイクを使う場合は歌い手とマイクの距離を変えて、環境音や残響音と声のバランスを調整します。歌い手とマイクが近づくほど、環境音に対する声の音量が増加します。
昨今では自宅でボーカルレコーディングすることも一般的になり、レコーディング用マイクもさまざまな製品が販売されています。別の記事で自宅レコーディングでのマイクの選び方や必要となる周辺機器を解説していますので、参考にしてください。